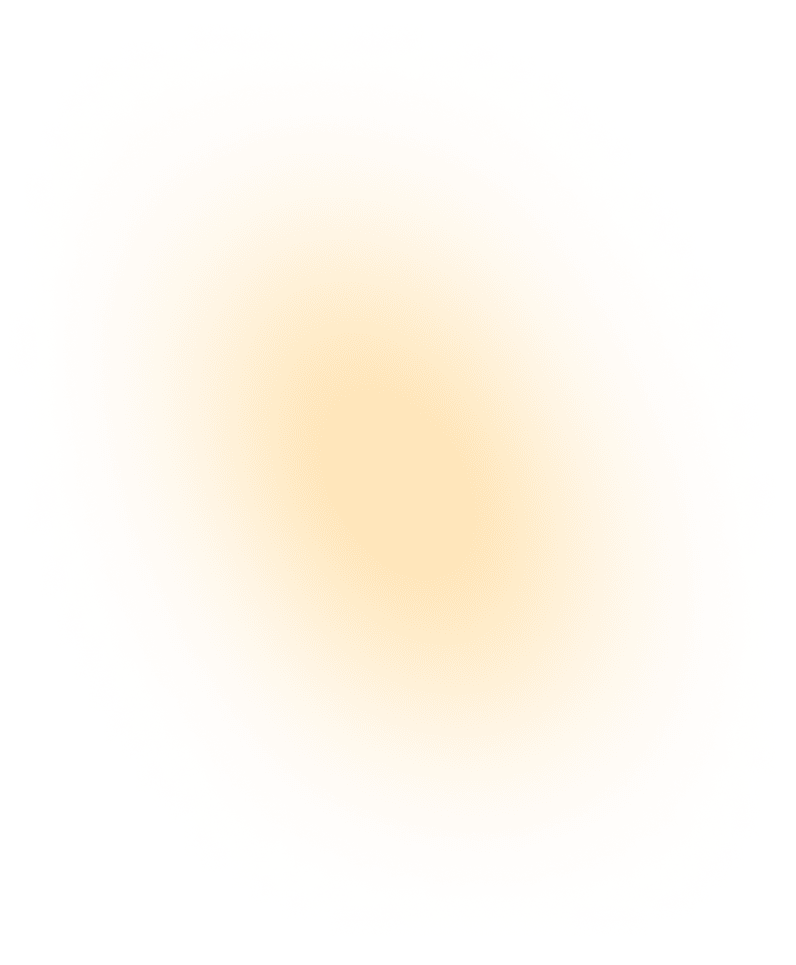- ① クチコミマーケティング業界の健全な発展のためには、情報発信者・情報受信者としてクチコミマーケティングを担う消費者を保護し、コミュニケーションの信頼性を損なう行為を排除すべきです。情報受信者には正しく情報を知る権利があります。情報発信者は、それを妨げてしまうと社会的信頼を失いかねません。虚偽やなりすましはもちろん、必要な情報を適切に明示しないことも、コミュニケーションの信頼性を損なう行為です。
- ② 知名度や影響力の大小に関わらず(著名人・芸能人であっても)、個人のアカウントでの情報発信の場合は「情報発信者(情報を発信する消費者)」とみなします
- ① 本ガイドラインは、日本国内の消費者を主な対象としているクチコミマーケティングに適用します。
- ② クチコミマーケティング協会の会員は、マーケティング主体・中間事業者・情報発信者いずれの立場でクチコミマーケティングに関与する場合においても、自身が関わる範囲では本ガイドラインを遵守しなければなりません。例えばWOMJ会員ではない企業から、WOMJ会員が中間事業者としてクチコミマーケティング業務を委託された場合でも、一連のクチコミマーケティングはWOMJガイドラインを遵守したものでなければなりません。
- ③ クチコミマーケティングとは、オンライン・オフラインを問わず、消費者間のコミュニケーションをマーケティングに活用することですが、本ガイドラインの適用範囲はオンラインのクチコミマーケティング(消費者がオンラインで発信する情報を、消費者がオンラインで受信するクチコミマーケティング)です。オンラインとは、ブログやソーシャルメディアだけでなく、掲示板サイト、ECサイト、アプリストアなど、消費者が投票したりコメントしたりできるメディアも含みます。また、文字・写真・画像・音声・映像など、表現の形態は問いません。
- ④ 自社の社員が自社や関連会社・取引先の事業などについて個人のSNSアカウントから発信する情報は、本ガイドラインの適用範囲に含まれます。
- ⑤ 情報発信者に対してオフラインで何らかの働きかけを行う場合でも、消費者同士の情報の受発信がオンラインで行われる場合は、本ガイドラインの適用範囲に含まれます。
- ⑥ ウェブ媒体の編集記事、自社媒体(ウェブサイト、オウンドメディア)、自社のSNSアカウントでの投稿などは、情報発信者が「消費者」では無いため、クチコミマーケティングには含まれず、本ガイドラインの適用範囲ではありません。
- ⑦ 本ガイドラインは、本ガイドラインの施行日以降に情報受信者が情報を受信しうるクチコミマーケティングに適用します。
- ① マーケティング主体の定義
「マーケティング主体」とは、一連のクチコミマーケティングを主催する企業や団体をいいます。一般的に、広告主や媒体社などであり、消費者からの問い合わせに対して主体として回答する立場にある企業や団体とします。 - ② 中間事業者の扱い
情報発信者に対する金銭・物品・サービスなどの提供者が誰であっても、関係性はマーケティング主体と情報発信者の間に発生するとします。クチコミマーケティングの業務を受託する中間事業者(主催者に含まれている場合を除く)は、マーケティング主体ではありません。 例えば、マーケティング主体であるA社から依頼を受けたB社が情報発信者C氏に重要な金銭提供を行う場合、C氏に直接接触するのはB社であっても、関係性はA社とC氏の間にあると考えます。関係性明示の際は、主体の明示ではA社が明示されなければなりません(B社を明示する必要はありません)。
-
【解説】
- アのaからdのいずれか一つにでも当てはまる場合には「関係性がある」とします。以下に、aからdの個々の判断基準を示します。
③ ア 関係性の有無の判断基準
- 1. 提供の目的
マーケティング主体と情報発信者との間に「関係性がある」といえるためには、金銭・物品・サービスなどの提供の目的がクチコミマーケティング(消費者間コミュニケーションのマーケティング活用)であることが必要です。情報発信者に対して金銭・物品・サービスなどの提供を行う場合でも、クチコミマーケティングが目的ではない場合には、「関係性がある」とは判断せず、関係性明示をする必要はありません。例えば、次のような場合はクチコミマーケティングが目的ではない物品等の提供であり、「関係性がある」とは判断せず、関係性明示は不要です。 - 2. 金銭・物品・サービスなどの範囲
情報発信者に提供する「金銭・物品・サービスなど」には、次のものを含みます。・商品券、電子マネー、会員専用ポイントその他の有価証券
・商品購入時の値引きや割引クーポン券
・イベントへの招待、イベントに参加できる特典
・その他、経済上の利益と考えられるもの
- 3. 「重要」な金銭・物品・サービスなどの提供
マーケティング主体と情報発信者との間に「関係性がある」といえるためには、提供する金銭・物品・サービスなどが「重要」であることが必要です。情報発信者に対して提供する金銭・物品・サービスなどが「重要」とはいえない場合、「関係性がある」とは判断せず、関係性明示は不要です。「重要」となるのは次のいずれかに当てはまる場合です。例えば、高額・希少な商品やサービスの提供、飲食・接待、招待者が限定されたイベント・パーティーへの招待などは「重要」と判断します。一方で、例えばイベント参加者への必要最低限の交通費の支給や、来場者にお茶を出すことなどは「重要」ではないと判断し、「関係性がある」とはしません。A) 金銭・物品・サービスなどの「提供の有無」により、情報発信者から発せられる情報に有意な差異が生じると考えられる場合。
B) 金銭・物品・サービスなどの提供という「関係内容の明示の有無」により、情報受信者の認識や行動に有意な差異が生じると考えられる場合。
・商品やサービスの試用そのものを目的とする、試供品やお試し券の提供
・懸賞当選者への景品提供
- 4. 情報内容の決定に関与する場合
マーケティング主体または中間事業者が情報発信者の発信する情報内容の決定に関与する場合には、「関係性がある」とします。次のような場合は「情報内容の決定に関与する場合」と判断します。・発信する情報内容について情報発信者に明示的な依頼・指示をする場合
・発信する情報内容について情報発信者に対して明示的な依頼・指示はなくとも、それに準ずると客観的に判断できる言動や行為により、情報発信者がマーケティング主体の商品やサービスに関する情報を発信する場合
・発信する情報内容について情報発信者に対して明示的な依頼・指示はなくとも、マーケティング主体が情報発信者に情報を発信することを依頼しつつ、マーケティング主体の商品やサービスを情報発信者に無償で提供し、その提供を受けた情報発信者が当該マーケティング主体の期待・意図する方針に沿う情報内容を発信する場合
- 5. 懸賞・キャンペーン応募のためのハッシュタグや、投稿内容の指定
懸賞・キャンペーン応募のためのハッシュタグ指定だけであれば、「関係性がある」とはしません。しかしながら、情報受信者の正しく情報を知る権利を尊重する観点から、懸賞やキャンペーン応募の際には、応募者にはハッシュタグ等の方法でマーケティング主体を明示させ、かつ「○○キャンペーン」「○○プレゼント」「○○コンテスト」など、「情報発信者が懸賞やキャンペーンに応募していること」が情報受信者に明瞭に伝わるような表記をさせることを推奨します。
一方で、マーケティング主体の商品・サービスの内容や取引条件に関する情報内容を指定する場合や、応募者識別以外の目的と考えられるハッシュタグを指定する場合は、「情報内容の決定に関与した」と判断されることがあります。また、その内容によっては法令等に抵触する可能性もあります。例:情報内容の決定に関与したと判断され、また法令等にも抵触する可能性があるハッシュタグ
・#私は食品Aが世界一大好き!!⇒商品の内容に関する情報発信者の主観的な感想を強制的に発信させている。
・#化粧品Aでシミが全部消えた!⇒薬機法や景品表示法に抵触するような内容
・#今期売上No1サプリメント⇒十分なエビデンスが無ければ訴求できない最上級表現 -
また、懸賞・キャンペーンの応募の条件として「自由に感想を書いて投稿してもらう」ことや、「予め設定した選択肢から選んで投稿してもらう」ことも直ちに「関係性がある」とは判断しません。しかし、「本来ならば情報発信者の主観的な感想に当たること」や「法令等に抵触するような内容」などを選択させたり、誘導したりするような場合には、「情報内容の決定に関与した」として、「関係性がある」と判断されることもあります。
例:情報内容の決定に関与したと判断され、また法令等にも抵触する可能性がある応募条件
・「この商品の一番優れているところをあなたの言葉で100文字以内で投稿してください
⇒本来十分なエビデンスが必要な表現を、詳細な条件無しに依頼・指示している。
・「この商品であなたが一番好きなところを、以下の選択肢から選んで投稿してください」
A効能効果がとんでもない
B広告のセンスが良い
C最高のコスパ
D多分国産だから
⇒個々の選択肢が「情報発信者の主観的な感想」と乖離している可能性が高く、他の選択肢も与えられていない。
- 6. マーケティング主体と情報発信者の「係わり」
マーケティング主体または中間事業者と、情報発信者との間に次のような「係わり」があれば、情報発信者の自主的な意志による情報内容とは客観的に認められないため、「関係性がある」とします。・雇用契約、販売代理店契約、業務委託契約などの契約関係
・業務の受発注などの取引関係
・その他、マーケティング主体や中間事業者が、情報発信者の発信する情報内容や情報を発信することそのものに影響を与えられる関係にある場合
- なお、これらの「係わり」は情報発信の時点では解消されていたとしても、過去に一定期間上記のような関係があった場合や、今後「係わり」が始まることが決まっている場合(今後「係わり」が実現する可能性を想起させる場合なども含みます)も、「係わり」があると判断します。
- 7. 自身の所属する組織
「自身の所属する組織」には、次のものも含みます。・自身の所属する会社のグループ会社・関連会社など
・自身の所属する組織の関連組織など
- 8. 利害関係にある組織
「利害関係にある組織」には、次のものも含みます。・取引関係のある企業・団体など
-
【解説】
- 1. 関係性明示義務
アのいずれか一つにでも当てはまる場合、情報発信者とマーケティング主体との間には「関係性がある」とされるため、マーケティング主体および中間事業者は、情報発信者にウの方法に従った関係性明示をさせなければなりません。 - 2. 関係性明示義務の例外
アのいずれか一つに当てはまり、「関係性がある」とされる場合であっても、クチコミマーケティングのターゲット層である情報受信者にマーケティング主体と情報発信者との間に「関係性がある」ことが十分に認知されているなど、「関係性がある」ことが情報受信者にとって社会通念上明らかである場合には、関係性明示を省略することを許容します。もっとも、情報受信者の正しく情報を知る権利を尊重する観点から、関係性明示を行うことを推奨します。例:「関係性がある」ことが情報受信者にとって社会通念上明らかといえる場合(関係性明示の省略を許容する)
・マーケティング主体のCMに出演していることに十分な認知があるタレント・著名人
・マーケティング主体であるスポンサー企業との関係が十分に認知さているアスリート
・マーケティング主体である自治体等の「観光大使」に任命され、十分な活動実績がある人物例:「関係性がある」ことが情報受信者にとって社会通念上明らかとはいえない場合(関係性明示が必要)
・マーケティング主体の公式SNSで一度だけ写真が紹介されたが、アンバサダーや広告契約などの実態には言及されていない人物
・広告やイベント出演などの実績が殆どなく、関係性が十分には認知されていない人物
・著名人が「実は声だけ出演している」など、関係性の周知が十分ではない場合
④ イ 関係性明示義務
-
【解説】
- 1. マーケティング主体の名称表記
マーケティング主体の名称表記は、企業や団体の正式名称、またはその通称や略称を推奨しますが、それ以外の表記も次のとおり許容します。<推奨>A 企業や団体の正式名称
B 企業や団体の通称・略称
<許容>C 商品・サービスのブランド名(略称可)
D 上記のABCとは異なる「仮の組織・団体名」
ただし、Dは情報受信者が容易に理解できる表記方法とは断定できないため、次の①から③の条件のすべてを満たす必要がある。 ① 「仮の組織・団体名」が組織・団体の名称だと容易に判断できる。(例:「**委員会」「**研究会」「**クラブ」は可、「**女子」「**大辞典」は不可) ② 「仮の組織・団体名」で検索すれば、その公式ウェブサイトや公式アカウントが容易に見つかる。 ③ ②の公式ウェブサイトや公式アカウントに、ABCのいずれかが明記されている。E 上記のABCDが含まれるキャンペーン名やキャッチコピー
- 2. ティーザー施策の主体表記の特例
ティーザー型キャンペーンでは、ティーザー期間中に限り、マーケティング主体の名称としてキャンペーン名や一時的な仮の名称の使用を認めます。ただし、ティーザー期間終了後は、本来のマーケティング主体の名称を明示しなければなりません。また、ティーザー期間中は、キャンペーン名や一時的な仮の名称のもとで、情報受信者からの問い合わせに対応できる機能を持たなければなりません。- 3. マーケティング主体が複数の場合
複数のマーケティング主体が存在する場合、明示するマーケティング主体は、クチコミマーケティングの実態に即して選択できるものとします。- 4. 関係内容の明示方法
(1) 「関係内容の明示」の方法として、次の「関係タグ」の使用を認めます。
関係タグ:
#プロモーション、#PR、#宣伝、#広告
※「#PR」は、パブリックリレーションズと混同のおそれはあるものの現状のクチコミマーケティングの実態に鑑み使用を許容します。
※上記以外の関係タグの使用は認めません。
※「#AD」「#pr」「#Promotion」などの英語表記・小文字表記は推奨しません。(2) 関係タグを用いる場合にもマーケティング主体の明示は別途必要です。
マーケティング主体の明示をハッシュタグで行う場合には、関係タグを先に記載してください。
なお、関係タグとマーケティング主体の名称を組み合わせて一つのハッシュタグにまとめることは認めません。
正しい例:
#PR #A社
正しくない例:
#A社 #PR、#A社PR、#PR A社(3) 複数のハッシュタグとともに関係タグを用いる場合、関係タグは必ず先頭に記載してください。
(4) 関係タグは「#PR」のようなハッシュタグでなく、【PR】のように表記することも認めます。
(5) 関係タグを用いずとも、マーケティング主体と情報発信者の具体的な関係の内容を明瞭に記載することも許容します。
例:○○○はマーケティング主体名
○○○のプロモーションに参加しています。
○○○の商品モニターに協力中です。
○○○から謝礼をいただいて投稿しています。
○○○から商品提供をいただきました。
○○○から献本いただきました。
○○○主催のイベントに招待されました。
○○○のPR案件としての投稿です。
私は○○○の社員です。
○○○でこの商品の販促を担当しています。
○○○の広告制作を担当しています。
○○○の広告に出演しています。(6) 次のような表記は、マーケティング主体と情報発信者の関係の内容が十分に理解できない(あるいは理解できない可能性が高い)ため原則として認めません。ただし、その表記が当該クチコミマーケティングのターゲット層に十分な認知がある場合に限り、例外的に使用を許容します。
例:
○○○はマーケティング主体名
○○○とのタイアップです。
○○○とのコラボレーション(コラボ)です。
○○○の案件です。
「#タイアップ」「#コラボ」など、関係タグのようなハッシュタグのみでの記載は許容しません。 - 2. ティーザー施策の主体表記の特例
⑤ ウ 関係性明示の方法
- 5. 明瞭な関係性明示
関係性明示は、情報受信者が容易に認識かつ理解できる明瞭な表示方法で行わなければなりません。
関係性明示は、情報受信者に容易に理解できる方法であれば、文字・写真・画像・音声・映像など、表現の形態は問いません。例えば、マーケティング主体の名称表記として企業名を文字で記載する代わりに企業名入りのロゴ画像を掲載することができます。次のような表示方法は関係性明示としては不明瞭なので許容しません。明瞭な方法の例:
・SNSプラットフォームの関係性明示機能を使用する(ブランドコンテンツタグなど)。
・動画の場合(概要欄など動画の外でなく)動画内かつ冒頭で行う。
・実況中継など長時間の動画では、冒頭だけでなく一定時間ごと(目安として15分に一度程度)に関係性明示を行う。不明瞭な方法の例:
・大量のハッシュタグの中に関係タグが埋もれている。
・長文の本文の末尾・長時間の動画の最後などで表示して、視認しにくい。
・SNS等の投稿で、長文が折りたたまれておりクリックしなければ見えない部分に表示する。
・SNS等の投稿で、最初の投稿ではなく、リプライやコメント欄で表示する。
・関係タグを周囲の文字より小さく表示する。
・関係タグを周囲の文字より薄い色とする。
・動画の概要欄のみで行い、動画内には何らの表示もない。
・プロフィール欄にのみ記載し、個別の投稿を見るだけでは関係の内容がわからない。
・投稿内にはリンク先URLが記載され、リンク先にいけば関係の内容がわかるが、投稿だけ見ても関係の内容がわからない。
・「#広告」という関係タグを使用しているにも関わらず、投稿内で「広告ではありません」と記述するなど、関係性があるのかないのかまぎらわしい。- 6. プラットフォームのルールの尊重
関係性明示について、ソーシャルメディアのプラットフォームに独自にルールがある場合は、それに従うことを推奨します。ただし、プラットフォームのルールが本ガイドラインの関係性明示と比べて不十分、あるいは不明瞭な場合には、プラットフォームのルール以上の関係性明示を行う必要があります。例えば、プラットフォームのルールでは「主体の明示」が不要とされている場合にも、「主体の明示」は行う必要があります。- 7. アフィリエイト
情報発信者の発信する情報にアフィリエイトが含まれる場合は、本ガイドラインだけでなく景品表示法などの各種法令等、および業界団体のアフィリエイトに関するガイドラインも遵守してください。 - 6. プラットフォームのルールの尊重
-
【解説】
- ① いいね!やフォローなどの投票行動に対価を支払い、評価を不正に操作すること
- ② 動画の再生回数など閲覧行動を、自動プログラムや人為的な反復により不正に操作すること
- ③ 口コミサイトなどで、虚偽の推奨コメント(または批判コメント)を投稿したり、実態のない評価を意図的に作り上げたりすること
- ④ 消費者から発信された情報を改ざんすること
- ⑤ マーケティング主体の競合相手の評判をおとしめること
- ⑥ その他、明らかに情報受信者をあざむく行為とWOMJガイドライン委員会が定めるもの
次のような行為は「クチコミマーケティングにおける偽装行為」に該当します。
-
【解説】
(違反への対応)WOMJ会員が本ガイドラインに違反した場合、もしくは違反の疑いがある場合、WOMJ運営委員会はWOMJ会員規約に基づいて会員の処分を検討します。また、違反(裁量範囲を超えた判断を含む)の疑いについて、WOMJ会員はWOMJ運営委員会から質問があれば回答しなければなりません。WOMJ運営委員会はその回答を他の会員に開示できるものとします。
-
2023年3月に消費者庁が公開した景表法の指定告示と運用基準によれば、ステルスマーケティングは「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」とされています。しかしながら景表法は商品やサービスの取引に関わる表示が対象の法律で、世の中には景表法の対象範囲外での「ステルスマーケティング」も存在すると考えられます。
一般的には「広告主がいるにもかかわらず、広告主が明示されない広告」、「広告という形態をとらずに行われるマーケティング活動で、主体が明らかにされないもの」、「本来の広告主とは異なる名称の主体によって行われる、広告・マーケティング活動のこと」などといわれています。 共通するのは「『広告・宣伝・マーケティング』であるとわからない」かつ「主体が明らかにされない」ことです。マーケティングであるという事実、あるいはマーケティングの主体が消費者から隠れている(ステルス)マーケティング活動であり、そのようなものが総称してステルスマーケティングと呼ばれています。
オンラインのクチコミ(消費者間のコミュニケーション)におけるステルスマーケティングは行われるべきではありません。
WOMJでは、WOMJガイドラインに準拠することで、ステルスマーケティングを防止できると考えています。
-
WOMとは「Word of Mouth」の頭文字で、日本語では「クチコミ」という意味です。
●2023年9月1日、WOMマーケティング協議会は一般社団法人クチコミマーケティング協会となりました。以前使用していた「WOMマーケティング」という言葉は「クチコミマーケティング」と言い換えます。
・クチコミに関するあらゆるマーケティング活動
・クチコミとは消費者間で行われる自発的なコミュニケーションである
-
WOMJでは「クチコミマーケティングは、広告的な要素をもちつつも、広告とは異なる広がりの可能性もあるマーケティング」と考えています。クチコミマーケティングは、マーケティング活動や宣伝の手法の一種ですが、以下の理由から広告とは異なる要素があると考えています。
・広告は、広告主がその内容に関して事前に全てを把握し、内容の責任を負うものです。
・それに対してクチコミは、消費者間で行われる自発的なコミュニケーションであり、原則としてその投稿内容は情報発信者に委ねられています。情報発信者の知人だけに伝わるような言葉遣い、あるいは知人間のプライベートに踏み込むような情報が記載されることもあります。
・多くの場合、事前にマーケティング主体(広告主*)はその内容の全ては把握していません。
・ここが、広告とクチコミの異なる要素です。
クチコミは、通常の広告文脈ではなし得ないコミュニケーションを形成することもあります。従来の広告の文脈ではとらえきれない伝わり方や広がりを示すのがクチコミマーケティングの特徴だと考えています。クチコミマーケティングは「広告とは異なる広がりの可能性もあるマーケティング」なので、WOMJガイドラインの本文と解説では「広告主」という言葉は用いず、「マーケティング主体」という言葉を用いています。
-
「クチコミ」は消費者間で行われるコミュニケーションなので、情報を発信する方も受け取る方もともに消費者です。
ガイドラインでは、単に「消費者」というと誤解を招くおそれがある箇所では「情報受信者」「情報発信者」と書き分けています。
-
WOMJガイドラインでは「正しく情報を発信しない」場合として、以下の2つを想定しています。
- ① 情報発信者が、マーケティング主体との間に「関係性がある」にもかかわらず、適切な関係性明示(主体の明示と関係内容の明示)をしない。
- ② 情報発信者が、実際にはやっていないことを「やった」と書いたり、意に反する評価を行うことでランキング操作などに関わる、フォロワーを買う、などの偽装行為を行う。
情報発信者による①②の行為が明るみに出た場合、情報発信者は「消費者を欺いた」として、社会的な信頼を失うことになります。WOMJではこれを情報発信者のリスクと考えています。
WOMJ会員がクチコミマーケティングに関わり、情報発信者に情報発信をはたらきかける場合にはガイドラインを遵守してもらうことによって、情報発信者のリスクを軽減・回避すべきと考えています。
-
WOMJガイドラインはWOMJ会員が遵守するものであり、同時にWOMJ会員が関与するクチコミマーケティングにおいて情報発信者(インフルエンサーなど)に遵守してもらうものです。
WOMJ会員以外の方においても、クチコミマーケティング業界の発展や消費者保護の観点から、WOMJガイドラインに準拠した運用を推奨致します。
-
情報発信者からのクチコミであっても、例えば次のような場合には、関係性明示は不要とされる場合があります。(以下のいずれかに当てはまる場合でも、他の要件から「関係性がある」とされる場合もあります)
- ・WOMJガイドラインの適用範囲外
- 「主に日本国内の消費者を対象としているクチコミマーケティング」ではない場合
- 「オンラインのクチコミマーケティング」ではない場合
- ・関係性明示が必須ではない場合
- 情報発信者に金銭・物品・サービスなどの提供を行なう場合でも、その目的にクチコミマーケティングを含まない場合
- 情報発信者に対して提供する金銭・物品・サービスなどが「重要」とはいえない場合
- マーケティング主体や中間事業者が、情報発信者の発信する情報内容の決定に関与しない場合
- 情報発信者とマーケティング主体(中間事業者含む)の間に「係わり」が無く、発せられる情報が「マーケティング主体や中間事業者とは無関係な第三者の自主的な意思によるもの」といえる場合
- 懸賞応募やキャンペーン参加のためにハッシュタグをつけているだけの場合
- マーケティング主体のCMに出演していることに十分に認知があるタレントからのSNS投稿の場合(「関係性がある」ことが情報受信者にとって明らかといえる場合)
-
著名人・芸能人であっても、個人のアカウントでの情報発信の場合は「消費者」とみなしますので、WOMJガイドラインの適用範囲内となります。
また、媒体社の編集者・ライター、TV番組制作関係者なども、編集記事・番組・企業の公式アカウントでの情報発信ではなく、個人のアカウントからの情報発信の場合はWOMJガイドラインの適用範囲となります。
-
一般的に企業・団体のホームページで紹介されているというだけでは「ターゲット層である情報受信者に十分な認知がある」とはならないと思われます。
-
まず、この情報発信は企業からではなく、一個人すなわち消費者からの情報発信なのでクチコミと考えます。また「情報発信者が自身の所属する組織に関する情報を発信」しているので、「関係性がある」となり関係性の明示が必要です。関係性の明示は明瞭に行わねばなりませんが、プロフィール欄での表記は「不明瞭な方法」となるため許容されません。個別の発信だけを見ても「社員が自社や関連会社の事業などについて発信している」と明瞭にわかるような関係性明示を行ってください。
-
個別の事情にも左右されるためWOMJとして具体的な期間は定めておりません。例えば1年以上前の「係わり」であってもそれまで長期間にわたり深い「係わり」があった場合には「関係性がない」と判断することが難しいこともあろうかと思います。過去に「係わり」かあった場合の判断基準は、情報発信者から発信される情報が「マーケティング主体や中間事業者とは無関係な第三者の自主的な意思によるもの」かどうかを第一にお考えください。判断に悩む場合には、消費者保護の観点から関係性明示を行なうことを強く推奨します。
-
情報発信者への働きかけがオフライン(リアルな場でのイベントなど)であっても、情報発信者と情報受信者とのやり取りがオンライン上で行われる場合には、オンライン上のクチコミマーケティング部分についてはWOMJガイドラインの適用範囲となります。
なおWOMJガイドラインに従えば「オンラインでのクチコミの創出」が目的に含まれる場合(例えばSNSでの投稿を依頼する場合)には関係性の明示は必要となりますが、そうではなく「商品の試用・体験」のみを目的とする商品サンプリングでは関係性の明示は不要です。
-
WOMJガイドラインでは、情報受信者の「正しく情報を知る権利」を尊重し、保護することを目的としています。世の中でステルスマーケティングと呼ばれるものの中には、マーケティング主体の名称を隠す、あるいは詐称するタイプのものもあり、それらは消費者を欺く「正しくない情報」です。WOMJではマーケティング主体の名称を明らかにすることも「正しく情報を知る権利」の尊重・保護の一つだと考えています。
なお景表法は「消費者の自主的かつ合理的な選択の確保」が目的であり、そのためには「広告」であることがわかれば十分との理由から広告主の名称表記までは求めていないものと理解していますが、WOMJガイドラインとはそもそもの目的が違うことから、そのような差異が生じているとお考えください。
-
試供品の提供目的が「商品の試用・体験」であり、クチコミマーケティングを目的としない場合には、商品を受け取った方がSNS投稿する際の関係性明示は不要です。しかし「この場でSNSに投稿してくれれば追加でもう一つ商品を差し上げます」などとSNSへの投稿を依頼する場合には、目的にクチコミマーケティングが含まれていると考えられ、その上で「重要な金銭・物品・サービスなどの提供」がある場合には、消費者が(投稿を強制してはいないので)自発的にSNSに投稿する場合であっても関係性明示は必要となります。
-
原則として「情報提供」は「金銭・物品・サービスなど」には含めません。ただし「情報提供」が明らかに経済上の価値をもつ場合や、受け取る側にとって「重要」なものだと判断できるような場合には、関係性の明示は必要となります。判断に悩む場合には、消費者保護の観点から関係性明示を行なうことを強く推奨します。
※WOMJガイドライン「1.目的」より抜粋
(イ) 情報受信者(情報を受信する消費者)の「正しく情報を知る権利」を尊重し、保護する。
(ウ) 情報発信者(情報を発信する消費者)が正しく情報を発信しないことにより社会的信頼を失うことを防止する。
-
金銭・物品・サービスなどの提供の目的にクチコミマーケティングが含まれ、かつ「重要」な提供ならば、情報発信者へのSNS投稿の依頼の有無にかかわらず、関係性明示は必要です。
※解説「3.関係性の明示①関係性の有無の判断基準」より抜粋
2.提供する金銭・物品・サービスなどが「重要」か否か
(ア) 金銭・物品・サービスなどの「提供の有無」により、情報発信者から発せられる情報に有意な差異が生じると考えられる場合。
(イ) 金銭・物品・サービスなどの「関係性明示の有無」により、情報受信者の認識や行動に有意な差異が生じると考えられる場合。
-
「重要ではない」とし、関係性明示は不要と判断できる場合が多いと思います。
※解説「3.関係性の明示①関係性の有無の判断基準」より抜粋
2.提供する金銭・物品・サービスなどが「重要」か否か
(ア) 金銭・物品・サービスなどの「提供の有無」により、情報発信者から発せられる情報に有意な差異が生じると考えられる場合。
(イ) 金銭・物品・サービスなどの「関係性明示の有無」により、情報受信者の認識や行動に有意な差異が生じると考えられる場合。
-
WOMJガイドラインでの「金銭」には、現金の他に以下のものを含めます。
・商品券・電子マネー・会員専用ポイントなど経済上の利益となるもの
・商品購入時の値引きや割引クーポン券
-
WOMJガイドラインでの「サービスなど」には、現金の他に以下のものを含めます。
・イベントへの招待。イベントに参加できる特典
・その他、経済上の利益と考えられるもの
-
「マーケティング主体」とは、一連のクチコミマーケティングを主催する企業や団体を指します。一般的に、広告主や媒体社などであり、消費者からの問い合わせに対して主体として回答する立場にある企業や団体とします。クチコミマーケティングの業務を受託する中間事業者(主催者に含まれている場合を除く)は、マーケティング主体ではありません。
「中間事業者」とは、クチコミマーケティングの主催者(マーケティング主体)と、情報発信を行う消費者との間に存在する事業者です。PR会社・広告会社・芸能事務所などは、ほとんどのクチコミマーケティングにおいてマーケティング主体(主催者)ではなく中間事業者となります。
なお、関係性明示を行う際に「中間事業者の名前」を示すことで関係性明示(主体の明示)はクリアしているとの誤解があります。例えば、中間事業者B社の会員が「企業A社の商品を推奨する特定の文言を含む投稿を行うことで、B社の会員ポイントを得る」仕組みでは、マーケティング主体はA社で、ポイント発行を行うB社は中間事業者です。にもかかわらず、その中間事業者の名称表記をもって「主体の明示」とするのは、誤った運用となります。
-
「Aネットワーク」が別の企業等から商品・サービスなどの提供を受け、それをインフルエンサーに提供している場合には「Aネットワーク」は中間事業者でありマーケティング主体ではないので、「Aネットワーク」と記載しても主体の明示を行ったことにはなりません。大本の商品・サービスを提供しているところがマーケティング主体です。
なお「Aネットワーク」が提供する自社の商品・サービスに関するSNS投稿ならばマーケティング主体は「Aネットワーク」なので、主体の明示は「Aネットワーク」で問題ありません。
-
情報発信者の主観による「本心(自主的な意思)」かどうかではなく、客観的にみて「無関係な第三者の自主的な意思による情報発信」と認められるかどうかが判断基準となります。例えばA社の商品の広告制作を請け負っている広告会社の社員B氏が担当商品についてSNS投稿をする場合、いくらそのB氏が「本心(自主的な意思)」からA社の商品についてコメントしたとしても、それは客観的にみて「無関係な第三者の自主的な意思による情報発信」とは認められないでしょう(「認められない」と考える人が大多数だと推察します)。また消費者保護の観点からも、情報受信者にはそのSNS投稿がどのような「係わり」がある人物による投稿なのか「正しく情報を知る」権利があり、WOMJその権利を尊重・保護すべきものと考えます。
-
まずSNSプラットフォーム側に独自の関係性明示のルールや機能が実装されている場合には、それに従ってください。ただしプラットフォーム側のルールがWOMJガイドラインの関係性明示とくらべて不十分、あるいは不明瞭な場合には、プラットフォーム側のルール以上の関係性明示を行ってください。
独自のルールや機能がない場合には、写真だけで十分に関係性明示ができないときは、写真とともに閲覧できる文章で補ったり、動画の場合には動画の中で明瞭な関係性明示を行ってください。
-
クチコミマーケティングの目的に応じて、関係性明示が必要とされる期間は様々な場合があります。
例えば、物品提供を伴うモニター企画の場合では、情報受信者の正しく情報を知る権利を保護する観点から、適切なモニター期間をあらかじめ定め、その期間中は関係性明示を行うことを推奨します。
また、イベント招待の場合には、招待されたイベントへの参加期間中はもとより、イベント終了後でもそのイベントに関係する投稿を行う際には、関係性明示が行われねばなりません。
一方で、例えば春物の衣料品の提供を受けた場合、春のシーズン中はその衣料品を着た写真を投稿する場合には関係性の明示は必要としつつ、シーズン終了後は関係性明示は不要とするという運用は許容されます。
-
消費者保護の観点からは両方とも明瞭に示すことが望ましいです。しかし余計に混乱を招くほどの長文記載となると本末転倒ともなり得るので、関係タグを用いることで完結かつ明瞭に関係性明示を行なうことが有効な場合も多々あるだろうと考えます。
-
関係タグとして認めているのは「#プロモーション、#PR、#宣伝、#広告」の4つだけです。
「#ギフティング」というハッシュタグを関係タグとして使用することは許容していません。
なお文章・音声などでマーケティング主体と情報発信者の具体的な関係の内容を説明することで関係内容の明示とすることは許容していますが、「ギフティング」という言葉は人によって解釈の幅が大きいので、十分な関係性明示(関係内容の明示)とはなりません。ギフティングという言葉は使わずに例えば「商品を提供いただきました」という記載としてください。
-
「PR」は良好な関係構築を意味する「パブリックリレーションズ」の略語でもあり、パブリックリレーションズの意味は「金銭などの提供があるコミュニケーション活動」とは異なります。
しかしながら日本における「PR」は上記の意味を離れ、特にクチコミマーケティングにおいて、企業からの便益の提供などを意味する表記方法として、既に広く使われています。
WOMJガイドラインでは、現状のクチコミマーケティングの実態に鑑み「PR」の使用を許容しています。
-
WOMJではクチコミマーケティングを「広告的な要素をもちつつも、広告とは異なる広がりの可能性もあるマーケティング」と考えています。しかしながらWOMJ会員からも「#広告」を使用したいという要望もあり、また消費者庁の「ステマ規制」の運用基準によれば「広告」という表示は「事業者の表示である」との判別が容易な例示の一つに挙げられていることから、消費者保護の観点で検討を行い、関係タグとしての使用を許容することと致しました。
-
まずSNSプラットフォーム側に独自の関係性明示のルールや機能が実装されている場合には、それに従ってください。ただしプラットフォーム側のルールがWOMJガイドラインの関係性明示とくらべて不十分、あるいは不明瞭な場合には、プラットフォーム側のルール以上の関係性明示を行ってください。
その上で、関係タグである「#PR」を使わない方法、例えば「○○○より商品を提供いただきました」などの方法で関係内容の明示を行なうのがよいと考えます。
-
貸与の場合にも物品提供の場合と同様に関係内容の明示が必要です。
その場合「#PR」などの関係タグを使用することで「無償提供」と同等に認識されることに抵抗がある場合には「A社から貸与頂きました」などの文章表記での関係性明示を行うことも一つの方法です。
-
「懸賞に当選する権利や、当選確率が上がる権利」は、「サービスなど」の提供に含まれると考えることも不可能ではありませんが、多くの懸賞では大多数の応募者は直接的に金銭・物品・サービスなどの提供を受けるわけではないため、「懸賞に当選する権利や、当選確率が上がる権利」は直接の提供に比べて「重要ではない」と考えられます。
- 例:情報内容の決定に関与したと判断され、法令等にも抵触する可能性があるハッシュタグ
- #私は食品Aが世界一大好き!!⇒商品の内容に関する情報発信者の主観的な感想を強制的に発信させているさせているさせているさせている
- #化粧品Aでシミが全部消えた!⇒薬機法や景品表示法に抵触するような内容
- #今期売上No1サプリメント⇒十分なエビデンスが無ければ訴求できない最上級表現
そのような場合に関係性明示を厳密に求めることは、かえってクチコミマーケティングの健全な発展の妨げになると考え「関係性がある」とはしないと決めました。
しかし、次のような場合には、マーケティング主体は発信する「情報内容の決定に関与した」と考えられるため「関係性がある」となり、関係性明示は必要となります。
-
雑誌やウェブメディアでの編集記事に関しては、そもそもクチコミマーケティングではないので、WOMJガイドラインに基づく関係性明示は不要です。
一方で、業務を通じて提供を受けた商品であっても、個人のSNSアカウントで紹介する場合には関係性の明示は原則として必要となります。関係性の明示が必要な商品提供は、例えば次のような場合です。
・新製品の発売前に発表会、キャラバンなどを通じて現品を提供された
・編集部宛、あるいは個人宛に直接現品が送付された
・メーカーからの貸出商品と併せて「編集部でお使いください」と既存商品が提供された
・個人のSNSで自費で購入した商品を推奨したところ、後日メーカーから同じ商品が提供された
・個人的に愛用している商品を知ったメーカーの広報担当者から、定期的にその商品が提供される
・メーカーの方との会食の際、お土産として商品が提供された
・本来参加資格のないファミリーセールに招待され、優遇価格で商品を購入した
-
無料招待サービスの目的にクチコミマーケティングが含まれていないならば、関係性明示は不要です。
ただし、「ぜひSNSにも投稿して下さい」「投稿した方には無料券を追加でサービスします」などSNS投稿の依頼・指示を行なう場合には、無料招待サービスが「重要」ならば関係性明示は必要となります。
-
「【解説】3.関係性の明示 ④ イ 2.関係性明示義務の例外」を参照ください。
- 例:「関係性がある」ことが情報受信者にとって社会通念上明らかといえる場合(関係性明示の省略を許容する)
- マーケティング主体のCMに出演していることに十分な認知があるタレント・著名人
- マーケティング主体であるスポンサー企業との関係が十分に認知さているアスリート
- マーケティング主体である自治体等の「観光大使」に任命され、十分な活動実績がある人物
- 例:「「関係性がある」ことが情報受信者にとって社会通念上明らかとはいえない場合(関係性明示が必要)
- マーケティング主体の公式SNSで一度だけ写真が紹介されたが、アンバサダーや広告契約などの実態には言及されていない人物
- 広告やイベント出演などの実績が殆どなく、関係性が十分には認知されていない人物
- 著名人が「実は声だけ出演している」など、関係性の周知が十分ではない場合
2. 関係性明示義務の例外
アのいずれか一つに当てはまり、「関係性がある」とされる場合であっても、クチコミマーケティングのターゲット層である情報受信者にマーケティング主体と情報発信者との間に「関係性がある」ことが十分に認知されているなど、「関係性がある」ことが情報受信者にとって社会通念上明らかである場合には、関係性明示を省略することを許容します。もっとも、情報受信者の正しく情報を知る権利を尊重する観点から、関係性明示を行うことを推奨します。
-
自社サイトからの情報発信はWOMJガイドラインの適用範囲外となります。
なお、景表法の指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準においては「事業者の表示」ともなり得るものなので、そちらをご参照ください。
-
「情報発信者に対して、クチコミマーケティングを目的とした重要な金銭・物品・サービスなどの提供が行われる場合」なので、関係性明示は必要となります。
-
観光地のクチコミマーケティングが目的の企画であれば、その観光地の紹介に関するSNS投稿は撮影中・撮影後にかかわらず、またインフルエンサーとの契約を超える範囲での投稿であっても、関係性明示が必要と考えます。
-
Instagram、Facebook上に情報発信者が投稿を行う際には、投稿本文中での関係性明示(主体の明示と関係内容の明示)ではなく、プラットフォームを運営するMetaによる下記ポリシーに従ってください。
Metaのポリシーでは、情報発信者は自身の投稿にスポンサーページ(マーケティング主体の公式アカウント)をタグづけすることが義務付けられています。
タグづけを実施いただいていれば、関係性明示としては十分なので、例えば#PRのような関係タグは不要となります。
なお消費者保護の観点から関係性の明示は重複して行っても構いません。なので、Metaの下記ポリシーに従って、スポンサーページがタグ付けされていれば、投稿本文中に#PRなどの関係タグを使用しても問題ありません。
Meta「ブランドコンテンツポリシーについて」:
https://www.facebook.com/business/help/653146638176520?id=1912903575666924
また、ブランドコンテンツについての詳細はこちらからご参照ください。
Meta「ブランドコンテンツについて」:
https://www.facebook.com/business/help/523975231703117?id=603237934047137
※ブランドコンテンツに関するお問い合わせリンクページ
https://www.facebook.com/business/help/
-
TikTok上に情報発信者が投稿を行う際には、投稿本文中での関係性明示(主体の明示と関係内容の明示)ではなく、プラットフォームを運営するByteDance株式会社の「TikTok上のブランドコンテンツ」のルールに従ってください。
TikTok上のブランドコンテンツ」のルールに従い、ブランドコンテンツ・トグルをONにすると、投稿に「プロモーション」のマークが表示されます(2022年9月時点)。
「プロモーション」という表示がされることから、関係性明示における「関係内容の明示」としては十分なので、「#PR」のような関係タグは不要となります。
消費者保護の観点から、関係性の明示は重複して行っても構いません。ブランドコンテンツ・トグルをONにして「プロモーション」表示がなされている投稿であれば、本文や動画の中で「#PR」などの関係タグを使用しても問題ありません。
ただし、現時点ではブランドコンテンツ・トグルをONにしてもマーケティング主体は表示されません(2022年9月時点)。関係性明示における「主体の明示」はこの機能だけでは表示されないため、「主体の明示」は、動画内やコメント等で別途行っていただくこととなります。
ByteDance株式会社「Tiktok上のブランドコンテンツ」の詳細は、こちらからご参照ください。
https://support.tiktok.com/ja/business-and-creator/creator-and-business-accounts/branded-content-on-tiktok
※ブランドコンテンツに関するお問い合わせ
pr-m@bytedance.com
-
「記載されていないことはやっても良い」ということではありません。
「解説」には現時点で、明らかに消費者の正しく情報を知る権利を侵害していると考えられるものを列挙しています。これ以外にも、明らかとまでは言えずともグレーな行為はあります。
WOMJでは今後も継続的に検討を行い、追加・修正も行う予定です。
WOMJガイドラインの本文及び解説の「4.偽装行為の禁止」参照
-
関係性明示をした上でのコメントならば、WOMJガイドラインには抵触しません。
-
日々の業務を通じて、インフルエンサーなどWOMJ会員以外の方にもガイドラインの遵守を促してください。
それが、情報発信者が社会的信頼を失うことを防止し、情報受信者の「正しく情報を知る権利」を尊重し保護することになります。
そして、その積み重ねがクチコミマーケティング業界の健全な発展に繋がると考えています。
-
日々の業務を通じて、インフルエンサーなどWOMJ会員以外の方にもガイドラインの遵守を促してください。
それが、情報発信者が社会的信頼を失うことを防止し、情報受信者の「正しく情報を知る権利」を尊重し保護することになります。
そして、その積み重ねがクチコミマーケティング業界の健全な発展に繋がると考えています。
WOMJ会員がガイドラインに違反した場合は、以下のように対応いたします。
(違反への対応)WOMJ会員が本ガイドラインに違反した場合、もしくは違反の疑いがある場合、WOMJ運営委員会はWOMJ会員規約に基づいて会員の処分を検討します。また、違反(裁量範囲を超えた判断を含む)の疑いについて、WOMJ会員はWOMJ運営委員会から質問があれば回答しなければなりません。WOMJ運営委員会はその回答を他の会員に開示できるものとします。
旧・WOMJガイドライン(2017年12月4日~2023年9月30日)はこちらからご参考ください。